前回のブログに引き続き、環境変化が多い4月5月のこの時期の子ども達のサポート法について、Clubhouseトーク会での話をまとめています。今回は『学校以外に安心できる場』について。
◆学校のコミュニティが苦手な子ども達
Clubhouseのトーク会中に話題に上がったのが
「学校より習い事の場の方がのびのびしている」「同世代より年上や大人と話している方が楽しそう」
という子どもが結構いるという点です。精神年齢が実年齢より高い子ども達にこの傾向が見られるようです。同世代の友達が盛り上がっている話題に面白みを感じなかったり、いつも同じ友達と行動する事に意味を感じなかったり。そんな本音を持ちつつも「ここで本音を言ってしまうと、友達の中で浮いたり仲間から外されてしまうかも」と考えとりあえず皆に合わせる大人対応をしている子もいます。わが子(長女)もそのタイプの一人。高校生になった時、小学5,6年頃の思い出話を聞いていたら
「クラスの女子達の人間関係が面倒くさすぎて、合わせてはいたけど早く学校が終わって塾に行きたいと毎日思っていた」
とカミングアウトされ、驚かされた事があります。中学
◆学校以外のコミュニティを持つ大切さ
もしお子さんが学校内でストレスを感じているようであれば、
また、仲良し親子の場合は、親子で共通の趣味を楽しむのも一策です。clubhouseでは「娘の好きなアイドルグループに親も興味を持って、一緒にライブ画像を見たり応援したりして、学校でのストレスを発散させている」という話も出ました。悩みを直接聞き出さなくても、別の角度でストレス発散させてあげるのも親の大切なサポート法だと感じました。
◆親でも先生でもない大人の存在
子ども達が自分らしく過ごすためにもうひとつ、私が常に推奨してきたことがあります。それは
子どもに親と先生以外の大人と関わりを持たせる という事です。
これは意識していないとできない事だと感じています。ご近所づきあいの薄い最近の子ども達が高校を卒業するまでに長期間に渡って関わる大人は、親・祖父母・学校の先生・習い事の先生 以外ほぼ存在しないケースが多いのです。前編のブログにも書きましたが、子ども達は「親にはいつも笑顔でいてほしいし、迷惑をかけたくない」という思いがあるため、親にはいい事しか報告せず、悩んでいる心の内は打ち明けず1人で抱えている子が多くいます。「祖父母や先生に相談しても、きっと親にも話が届いてしまう」と考えれば、彼らにも話さないでしょう。
そんな時、親や先生よりもう少し子ども達に年齢の近い、20代~30代くらいの大人の存在が必要だと思うのです。例えば、学校の放課後サポートや学童に大学生(先生を目指す教育学部の学生達)を数多く招いたり、習い事教室にOBOGが参加できるようにする等、子ども達がこの世代の大人と接点が持てるしくみ作りができれば、子ども達は今ほど1人で悩みを抱え込まずに済むと思うのです。深い繋がりがなく共通の知り合いがいないからこそ何でも話しやすい上、年齢が近いため先輩としてのアドバイスが子どもの心に響きやすいと思うのです。
とはいえ、現実にはこのようなしくみ作りはまだ進んでいませんから、ここは親が工夫する必要があります。親の知人のお子さん(大学生)や会社の若手メンバー等と普段から接点を持たせてあげるのがよいでしょう。
ちなみに私の娘2人には、彼女達が幼少期から一緒にスキーやBBQに毎年行くなど家族ぐるみでおつきあいをしている30代の知人がいて、何かと相談に乗ってもらっているようです(^ ^)
『わが子が何でも話せる大人との接点』を普段から持ってあげてくださいね。

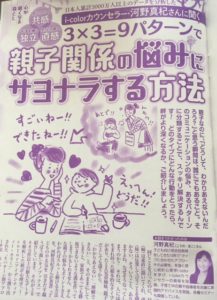
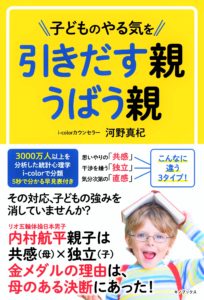
“環境変化が多い時期の子どものサポート【後編】ー学校以外に安心できる場ー” への 1 件のフィードバック
コメントは受け付けていません。